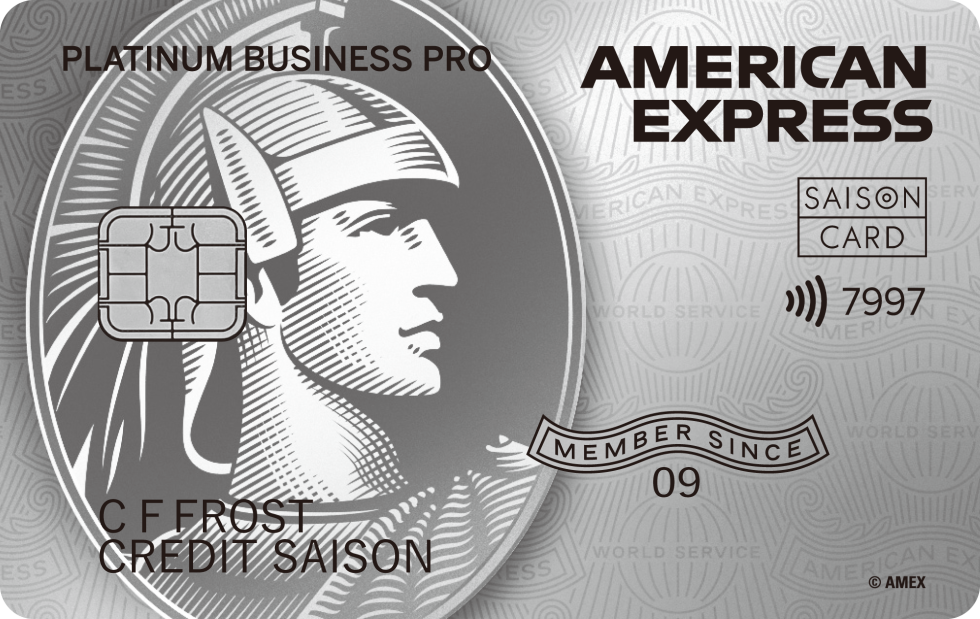企業会計の原則となる原価計算基準の基礎知識
財務諸表の作成に欠かせない原価計算基準とは?
経営における意思決定や財務諸表の作成など、原価計算は企業経営のあらゆるシーンで必要となります。それを行う上で規範となるのが原価計算基準です。企業会計原則の一環をなすものとして、1962年に当時の大蔵省企業会計審議会から公表された会計基準で、各企業が原価計算を実施する際は原価計算基準を遵守することが要請されています。
原価計算基準の目的
原価計算基準では、原価計算の主な目的として、以下の5つが挙げられます。「財務諸表の作成」のみ対外的な目的であり、その他は経営判断や社内管理を目的としています。
1.財務諸表の作成
企業は出資者や債権者などの外部利害関係者に向けて、過去一定期間の損失や期末時点での財政状態を、財務諸表により示すことが義務付けられています。
財務諸表は一般的に公正妥当と認められる会計慣行に基づいて行われなければならないとされ、多くの企業では原価計算基準に基づいて財務諸表作成が行われています。
原価計算基準に基づく原価計算により、売上原価や棚卸資産を算定し、損益計算書や貸借対照表の作成に反映されることになります。
2.価格管理
企業が商品やサービスの価格を設定するにあたり、原価の的確な把握は不可欠です。正確な原価計算により原価の実情を把握することで、企業にとって最適な価格を導き出せるでしょう。
ただし、原価計算基準における「価格計算」は、政府や公企業などへの納入価格を意識したものであり、企業が業務的意思決定として行う価格計算は想定されていません。そのため、完全競争の市場で活動する企業にとっては、適切ではない目的と考えられています。
3.原価管理
コスト削減や予算達成を実現するためには、原価を適切に管理することが重要です。原価管理では、標準原価や原価予算を算出し、実際原価との差異分析を行い、課題を洗い出しながら改善策を講じることになります。
原価計算基準における「原価管理」とは標準原価計算を利用します。実際原価をコントロールするために「原価統制」や「原価維持」を意味しています。原価目標水準を維持することを主眼とする、狭義の原価管理にすぎません。
一方、現代的な意味での原価管理とは、原価企画や原価改善などの原価計画を含み、包括的な利益管理を意図した、広義の原価管理(コストマネジメント)です。
4.予算管理
当期の事業目標を金額で設定し、実績との比較を定期的に実施するのが予算管理です。予算管理のプロセスは、予算編成のフェーズと予算統制のフェーズに分けられます。
予算管理では、予算実績比較による業績評価を基に、長期経営計画と大綱的短期利益計画が設定されます。予算編成方針を各部門へ伝達し部門予算が設定され、経営者による調整・承認が行われるまでのプロセスが、予算編成のフェーズです。
予算統制のフェーズでは、予算の提示を受けた後に活動を実行し、実績値や予算値の定期的な比較が実施されることになります。
原価計算基準では、製品組合せの決定や部品の自製・外注の選択など、業務的意思決定も予算編成の過程に含まれると規定されています。
5.経営における基本計画の設定
原価計算基準においては、経営の基本計画を設定する際、必要な原価情報を提供することが求められています。
基本計画とは、製品・立地・経営構造などに関する経営意思を定め、経営構造を合理的に形成することをいいます。必要に応じて随時行われるべき決定です。
原価計算基準の問題点
原価計算基準は、企業のシステム設定における一つの指標となってきたことや、教育の現場で必ず参照されてきたことなど、その意義や貢献は決して小さなものではありません。
一方で、1962年に制定されて以来一度も改定が加えられておらず、内容的にも陳腐化した部分があることが指摘されています。
特にこの十数年で、原価計算や会計管理の領域では実務的にも大きな変化が起こっており、昨今は財務諸表の作成時のみ原価計算基準を参照している企業も多いです。
これまで一定の役割を果たしてきたといえる原価計算基準の本質は理解しつつ、複数の原価計算制度を構築する方向で検討するなど、業界や企業のニーズに則した視点を持つ必要があるでしょう。
特性に合わせて使い分けたい3種の原価計算の方法
原価計算は標準原価計算・実際原価計算・直接原価計算の3種類に分けられます。それぞれの特性を考慮した使い分けが必要です。
方法1:標準原価計算
製造に必要な労働力や材料の消費量を統計的に調査し、製造時の目標値として算定する原価を標準原価といいます。原価計算基準では、「標準消費量×予定価格または正常価格」の計算式が設定されています。
計算が容易で速報性に優れている反面、誤差が出やすいというデメリットがあります。標準原価は実情に合わせて適宜改定されます。
方法2:実際原価計算
経営の正常な状態を前提とする財貨の実際消費量をもって計算した原価を実際原価といいます。実際の取得価格で計算した原価の発生額だけでなく、予定価格等を使用して計算した原価も含む考え方です。
原価計算基準では、「実際消費量×実際価格または予定価格等」の計算式が設定されています。予定価格等とは、長期平均価格としての正常価格を意味すると解されています。
標準原価と実際原価を比較することで、業務の課題解消や効率化を図れる原価管理が可能となります。また、どちらの価格にも予定価格等の使用が認められているため、標準原価と実際原価の本質的な違いは消費量にあるといえます。
方法3:直接原価計算
原価を固定費と変動費に分けて考え、実際原価をさらに一歩進めた計算方法が直接原価計算です。製品ごとの原価率や利益を把握しやすいというメリットがあります。
売上と利益が比例していないと感じられる場合や、見せかけの利益のみ大きくなっていると感じる場合には、直接原価計算を実施すると実態を捉えやすいです。
直接原価計算は、変動費である直接原価を売上高から控除して貢献利益を算定し、貢献利益から固定費である期間原価を控除して営業利益を導き出す計算方法です。
したがって、CVPの関係を分析し、損益計算書で示せるように構築された計算方法にほかなりません。また、変動費用のみで製品原価を算出することから、変動原価計算ともいわれます。
原価計算で参入しない項目(非原価項目)
原価計算基準からの要請により以下に挙げる項目は非原価項目として扱い、原価に算入してはなりません。非原価項目は、製品の製造・販売に関係のない費用や損失などが該当します。
会計実務としては、何が原価で何が非原価かという問題は、比較可能性を担保できるかどうかで判断することになるでしょう。
1.経営目的に関連しない価値の減少
不動産投資・有価証券・貸付金などは、基本的に余剰資金を運用して行われるものであるため、これらの資産にかかる減価償却費・管理費・租税は原価に含まれません。
未稼働の固定資産や長期休止中の設備も、経営目的に関連している資産とはいえず、これらの資産から発生する減価償却費や管理費は非原価とされます。
支払利息・手形売却損・社債利息・社債発行費償却など、資金調達のために発生した費用は、営業外費用に分類されるため原価にはなりません。寄付金なども経営目的に関連しない支出です。
2.異常な状態が原因の価値の減少
異常な状態が原因で発生した特別損失にあたる費用は、原価に参入できないとされています。通常では発生し得ない仕掛品の破損や材料の蒸発・遺失などが該当します。
火事・地震・台風などによる災害や、盗難、労働争議・ストライキなどで損失が発生した場合も、原価には参入できません。
想定外の陳腐化などにより固定資産に著しい原価が生じた場合の臨時償却費も非原価として扱われます。なお、現在は「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が優先されており、臨時償却自体が廃止されています。
その他、延滞料・違約金・罰課金・損害賠償金・偶発債務損失・訴訟費・臨時的な多額の退職金・固定資産の売却損や除却損・異常な貸倒損失なども、異常な状態で発生した費用であるため、原価には参入しません。
3.税法上認められている損失算入項目
会計項目の中には会計的に費用として認められないものの、税法的には損金として認められるものがあります。このような性質を持った項目も原価には参入できません。
例えば、価格変動準備金繰入額や、租税特別措置法による償却額のうち通常の償却範囲額を超える額は、損金として認められることはあっても、原価には参入できないこととなっています。
4.その他の利益剰余金に課する項目
利益準備金以外の利益余剰金を指す「その他の利益剰余金」を取り崩して発生する費用は非原価です。
法人税・所得税・都道府県民税・市町村民税といった「法人税等」は、会計上は費用計上できます。ただし、税引前当期純利益を利益余剰金として捉えると、これらの税金は利益余剰金から国に支払うものと考えられるため、原価には参入されません。
配当金と任意積立金は、その他の利益剰余金から支払われるものであるため、非原価です。ただし、配当に関しては、その他資本剰余金からの支払いも現在は認められています。
原価計算基準では役員賞与金も非原価とされているが、現在は役員賞与金の繰り入れを費用として計上するため、原価となり得ます。同じく非原価とされている建設利息償却は、現在は廃止されています。
原価計算における原価計算基準の位置付けを理解しよう
原価計算基準は、制定当時の企業における原価計算の慣習を基に、一般に公正妥当と認められる部分を要約して作成されたものです。
基準の本質はあくまでも実務の拠り所であるため、弾力性を持つものであるという理解のもとで、それぞれの企業の実情に合った形で適用されるべきでしょう。

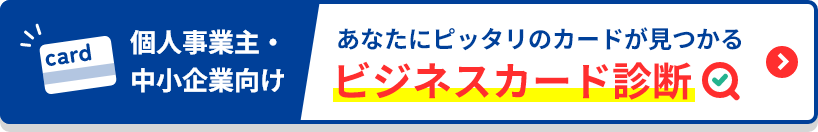
sbs.png)
sbs.png)