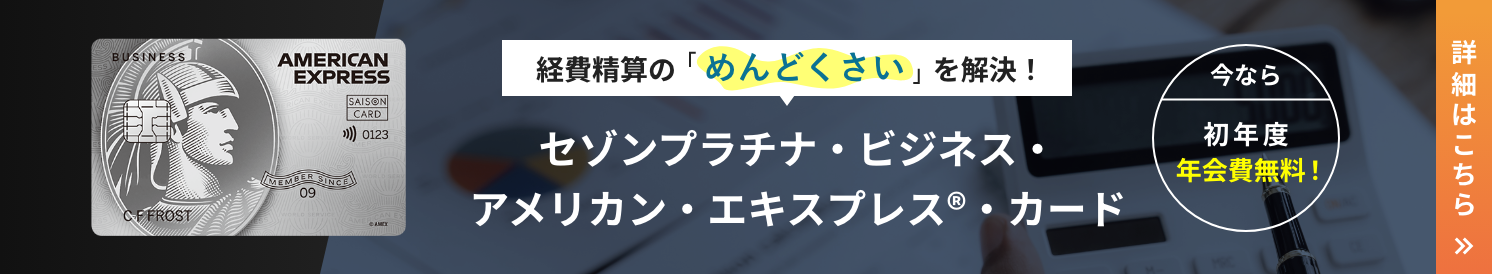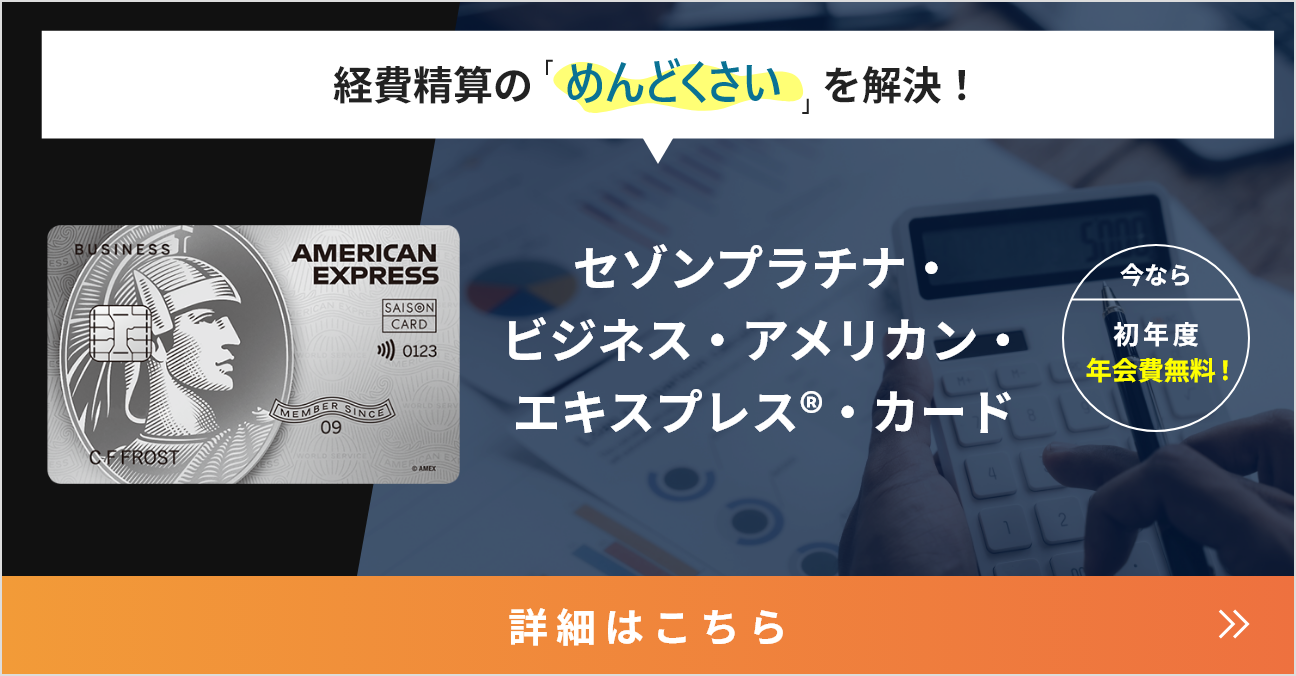副業の確定申告はいくらからすべき?計算方法、申告の種類、対処方法を解説
ここでは副業することによって必要となる確定申告への対処法をご紹介します。
副業の基準・定義
そもそも副業とは、一般的に本業以外で収入を得ている仕事のことを指しますが、法律などによる明確な定義はありません。そのため副業の基準は、勤めている企業によって異なります。一般的に本業以外でパートやアルバイトをして収入を得ている場合は、副業とみなす企業が多いのですが、株式やFXなどの投資が副業にあたるかどうかは就業規則などを確認してみないとわかりません。
また、金融機関などの場合は副業に該当するかどうか以前に、投資自体が禁じられています。金融機関の場合は上場企業の内部情報に触れる機会があり、その企業の株式に投資するとインサイダー取引に該当する可能性があるためです。
ただ、日本国憲法第22条では「職業選択の自由」が保障されており、副業を禁止する法律は存在しません。つまり、本業の就業時間外であれば、原則として誰でも自由に副業を行うことができます。
アルバイトやフリーランスとの違い
アルバイトは企業と雇用契約を結び、会社が定めたルールに従って働く形態です。会社との雇用契約により、従業員の責任は会社が負い、経費や保険も会社が負担します。一方、副業は本業との兼ね合いで、時間や場所を調整しながら追加の仕事を行います。
副業とフリーランスの最大の違いは、雇用契約を結んでいる本業の有無です。フリーランスは企業との雇用契約を結ばず、業務委託契約のみで仕事を行うことを本業としています。フリーランスは職種や業務内容、場所、時間帯を自分の裁量で自由に選べますが、副業は本業との両立を図りながら、空いた時間で追加の仕事を行います。
確定申告に関しては、フリーランスの場合は事業所得として確定申告が必須となります。一方、副業の場合は、副業所得が20万円未満であれば確定申告は不要です。本業での所得については会社が年末調整を行い、所得税も給料から自動で天引きされます。
確定申告が必要なのはいくらから?20万円以下は不要?
これまで会社員として働き、本業しかやってこなかったという方は確定申告を行う必要がないため、今まで一度も確定申告をしたことがないという方も多いのではないでしょうか。そこではじめに、確定申告がどのような場合に必要となるのかについて説明します。
所得が20万円を超えるなら確定申告が必要
副業を行うといっても、稼げる金額は人によって幅があります。では、副業を行った場合、いくら以上収入や所得を得ると確定申告が必要になるのでしょうか?一般的に副業による年間の収入や所得の合計が20万円を超えた場合は、確定申告が必要になります。つまり合計金額が20万円以下なら基本的に確定申告の必要はないということです。
●会社員の場合
会社員が副業を行う場合、年間の副業収入が20万円以上になると確定申告が必要となります。本業の給与収入については、会社が年末調整を行うため、通常は確定申告は不要です。ただし、給与収入が2,000万円を超える場合は、本業分も含めて確定申告が必要になります。
<給与所得者の確定申告が必要なケース>
● 副業収入が年間20万円以上ある場合
● 医療費控除などの各種控除を受ける場合
● 複数の収入源がある場合
副業収入は、経費を差し引いた所得に対して課税されるいうのが注意すべきポイントは。経費として認められる項目(交通費、材料費、通信費など)は確実に記録を残しておくことが重要です。また、確定申告の期限は毎年2月16日から3月15日までとなっています。
●アルバイトの場合
アルバイトとして働きながら副業を行う場合も、基本的な確定申告のルールは会社員と同様です。アルバイト収入と副業収入の合計が所得税の課税最低限(給与収入で103万円)を超える場合、確定申告が必要になります。
アルバイト収入が103万円未満でも、副業収入と合算して課税対象となる場合があります。例えば、アルバイト収入が90万円で副業収入が30万円ある場合、合計所得が課税対象となるため確定申告が必要です。
アルバイトの場合、通常は社会保険に加入していないため、国民健康保険や国民年金の保険料は自身で納付する必要があります。これらの保険料は、確定申告時に社会保険料控除として申告することができます。
所得20万円以下で確定申告が必要となるケース
副業といってもその業務形態はさまざまで、どんな形態(パートやアルバイト・個人事業など)かによって20万円以下という基準の考え方は変わってきます。例えば副業にパートやアルバイトを選んだ場合、そこから得たお金は既に必要経費などを差し引かれたものであるためすべて収入となり、年間20万円を超えると確定申告が必要です。
一方、自分でブログを運営し、その広告収入が年間25万円だった場合、運営に必要な経費が7万円かかったとすると年間の所得は18万円ということになり、確定申告の必要はありません。つまり単純に副業で得たお金の合計金額だけで確定申告が必要かどうか決まるわけではないということです。
そもそも所得とは?雑所得と事業所得の違い
そもそも所得とは、簡単にいうと会社員の場合は、給与から給与所得控除を差し引いたものであり、個人事業主の場合は収入から必要経費を差し引いたものです。会社員の場合は、給与明細に記載されている「総支給額」というのがいわゆる所得で、そこから税金や社会保険料などを引かれて銀行口座に振り込まれる金額が手取りです。
所得には、雑所得と事業所得があります。
事業所得は農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得を指します。一方、雑所得は他の所得区分に該当しない収入で、副収入やハンドメイド品の販売などが該当します。
2022年10月の国税庁による基準改定により、明確な判断基準が示されました。年間収入が300万円以下でも、帳簿書類をきちんと保存している場合は原則として事業所得として区分されます。
事業所得として認められるためには、継続的で安定した収入があり、営利目的であることが重要です。さらに、本業と同等の時間を費やしており、職業として社会的に認知されていることも判断要素となります。
雑所得の代表的な例としては、フリマアプリやネットオークションでの収益、副業のアフィリエイト収入、趣味のハンドメイド作品の販売などが挙げられます。一方、事業所得は継続的な製造・販売活動や、専門的なサービス提供、帳簿管理を伴う事業活動などが該当します。これらの活動が計画的かつ反復的に行われ、収益を上げる目的で実施されている場合は、事業所得として認定される可能性が高くなります。
副業の所得を計算する方法とは?
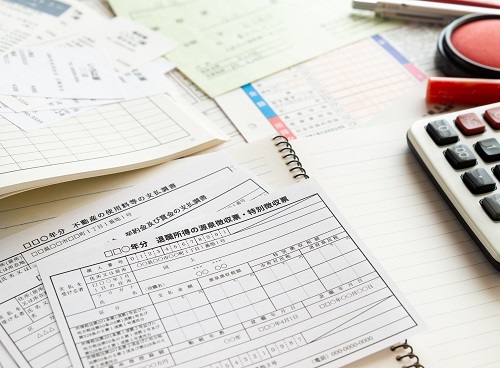
ここまでは、副業を行った場合に確定申告が必要となるケースについて解説してきました。では、その副業で得た所得はどのように計算すればいいのでしょうか?
所得金額の計算方法
所得金額というのは、上述したように収入金額から必要経費を差し引いた金額のことです。その計算方法ですが、上記でもご紹介したブログを運営して広告収入を得た場合で考えてみましょう。所得金額の計算方法は、いたってシンプルです。広告収入が年間20万円だったとしてブログの運営にかかった経費が5万円だった場合、20万円から5万円を引いた15万円が所得金額ということになります。
課税所得金額の計算方法
課税所得金額の計算方法を解説する前に、まずは所得と課税所得の違いについて解説しましょう。所得は既に説明したとおり、収入から必要経費を差し引いたものです。そこからさらに所得控除と呼ばれる控除金額を差し引いたものが課税所得となります。
所得控除には医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの種類があります。年末調整の書類を記入したことがある方はご存知の方も多いかもしれません。課税所得金額の計算方法は、上記で計算した所得から所得控除を引けば算出できます。
所得税の計算方法
所得税に関しては、副業で得た所得だけで計算するわけではありません。副業で得た所得と本業で得た所得を合わせて課税所得金額を算出し、その金額に対して決められている税率を掛けて、その金額から課税控除額を引くと所得税が算出できます。
経費として認められるもの
副業での経費は、その収入を得るために直接必要な費用のみが認められます。通信費については、副業専用の携帯電話代やインターネット料金が該当し、個人使用との按分が必要となります。交通費は業務に直接関係する移動の実費が計上でき、自家用車を使用する場合はガソリン代や駐車場代も経費として認められます。また、パソコンやタブレットなどの機器類は、取得価格が10万円未満なら全額経費計上が可能です。
副業の収入を適切に管理するためのポイント
収入や経費を適切に管理していないと、税務調査の対象となるリスクが高まります。特に、経費の過大計上や収入の計上漏れは、重加算税などのペナルティの対象となる可能性があるため、注意しましょう。
では、どのように管理するのが良いのでしょうか?
事業収支の透明性を確保するため、副業専用の銀行口座とクレジットカードを作ることをお勧めします。個人の支出と事業の支出を明確に区分することで、確定申告時の経費計算が容易になり、税務調査にも対応しやすくなります。
収支の記録は、取引の都度、日付、取引内容、金額を記帳することが重要です。デジタル帳簿の場合でも、領収書やレシートは原本を7年間保管する必要があります。特に事業所得として申告する場合は、青色申告を視野に入れた複式簿記での記帳が有利です。収支内訳書や確定申告書の作成時に必要な情報をいつでも確認できる状態に整理しておくことで、適切な税務申告が可能となります。
また、クラウド会計ソフトやスマートフォンアプリを活用することで、効率的な経費管理が可能です。レシートをスマートフォンで撮影して保存し、自動で経費として仕分けできるサービスも増えています。ただし、デジタルツールを使用する場合でも、原本の保管は必須です。
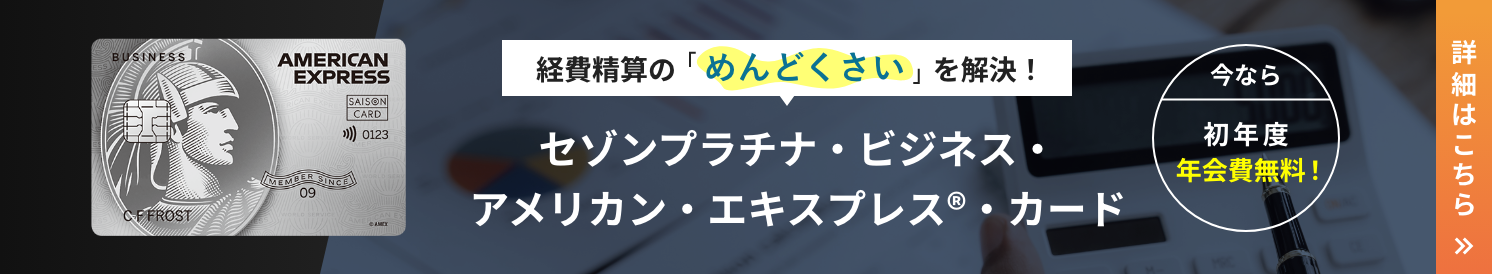
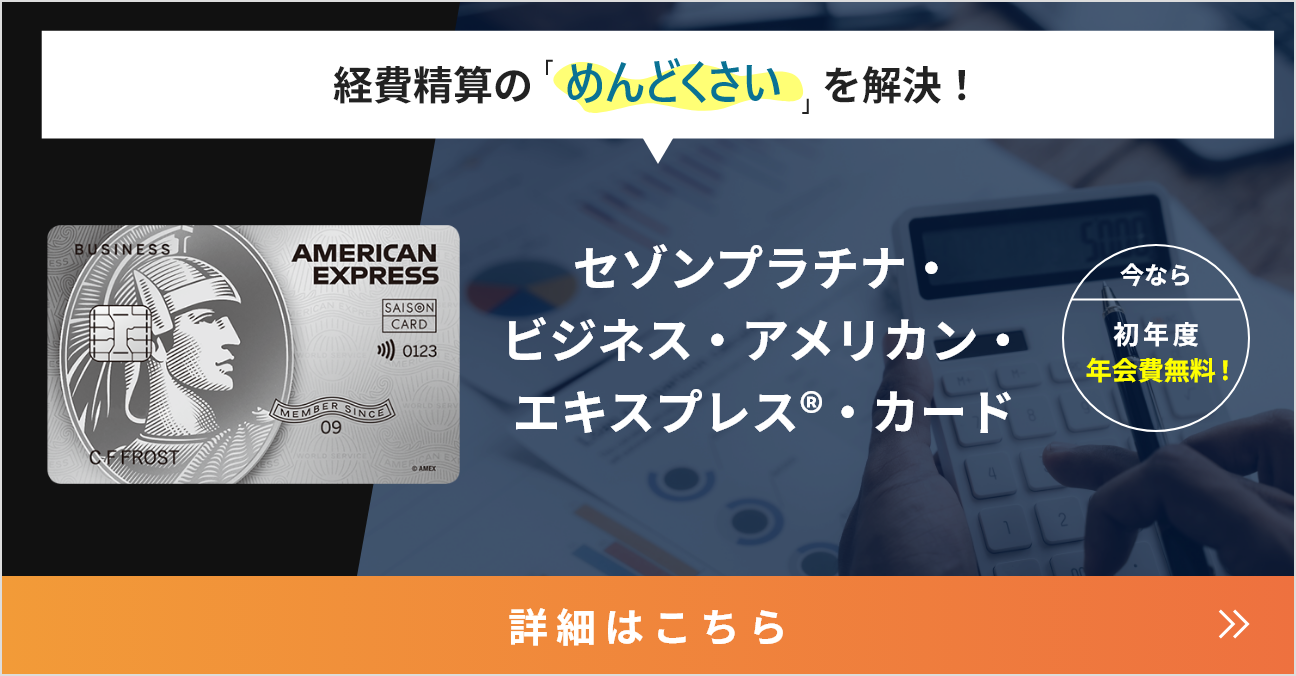
副業の確定申告は白色申告か青色申告か?
確定申告には白色申告と青色申告の2種類がありますが、副業を行って確定申告する場合はどちらで申告するのがいいのでしょうか?ここでは白色申告と青色申告、それぞれのメリットとデメリットについてご紹介します。
白色申告とは?
白色申告とは帳簿作成は簡単ですが、その分税制上のメリットを受けられないという申告方法です。青色申告をするためには、事前に税務署へ「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しておかなければならず、この届出を事前にしていない場合は自動的に白色申告ということになります。
・白色申告のメリット
白色申告のメリットは、何といっても申告手続きがシンプルで簡単に記帳できる点です。収支内訳書に売上と経費などを記入していくだけというお小遣い帳のような感じで、経理の知識がない人でも簡単に記入できます。また、青色申告のように事前に届出が必要ない点もメリットのひとつです。
・白色申告のデメリット
白色申告のデメリットは「青色申告特別控除」や「青色事業専従者給与」といった控除を受けることができない点です。ただ、これらの控除に関してはある程度の事業収入がある場合には大きなメリットとなりますが、事業収入が少ない場合は控除の恩恵も少ないため、それほど大きなデメリットにはなりません。
青色申告とは?
青色申告とは、正規の簿記の原則に従って作成された帳簿を備え、そこに日々の取引を記帳し、その記録に基づいて行う申告方法です。また、上述したように税務署への開業届と青色申告承認申請書の事前提出が必要になります。
・青色申告のメリット
白色申告のデメリットの項目でもご紹介しましたが、「青色申告特別控除」や「青色事業専従者給与」といった控除を受けられ、節税対策になる点が青色申告最大のメリットです。ある程度の事業収入がある場合は、青色申告したほうが節税対策になるなど大きな恩恵を受けられます。
・青色申告のデメリット
青色申告のデメリットのひとつは、開業届や青色申告承認申請書を事前に税務署へ提出しておかなければ、申告できないという点です。承認申請書に関しては、年度の途中で開業した場合、開業から2ヵ月以内に提出しなければなりません。また、複式簿記で帳簿を記入する必要があるなど申告方法が面倒な点もデメリットと言えるでしょう。
副業で確定申告をする際の注意点とリスク管理
副業の確定申告における注意点とリスク管理について、重要なポイントを解説します。
確定申告を怠った場合のリスク
確定申告を行わなかった場合、本来納めるべき税額に加えて重い追徴課税が課されます。具体的には、無申告加算税として15%(事前通知前の期限内申告の場合は5%)が課され、さらに延滞税として年2.4%〜8.8%が加算されます。悪質な場合は、重加算税として本来の税額の40%が追加で課される可能性もあります。
住民税と会社への影響
確定申告の漏れは住民税にも影響を及ぼします。
副業収入が発覚した場合、過去の住民税が遡って課税され、一括での支払いを求められる可能性があります。また、会社での住民税の特別徴収において、急な税額変更が発生し、会社に副業の存在が露見するリスクがあります。ただし、確定申告自体は税務署との個人的なやり取りであり、会社に通知されることはありません。
過剰な経費計上は税務署から指摘される
税務調査では、特に自宅の家賃や光熱費の全額計上、家族への給与支払い、高額な接待交際費などの経費計上が厳しくチェックされます。経費は事業との関連性が明確で、金額が適正である必要があります。税務調査で指摘を受けた場合は、速やかに修正申告を行い、追加の税額を納付することが重要です。
確定申告における書類の保管方法と重要性
確定申告関連書類は、青色申告の場合7年間、白色申告の場合5年間の保存が法律で定められています。領収書、請求書、契約書などは日付順に整理し、デジタルデータとしても保存することを推奨します。特に、取引の証拠となる原始書類は、スキャンデータだけでなく原本も保管する必要があります。書類は項目別にファイリングし、必要な時にすぐに取り出せる状態にしておくことが重要です。
副業における確定申告の必要書類
副業の確定申告に必要な書類について、体系的に解説します。
共通で必要な3つの書類
●確定申告書(確定申告書AまたはB)
確定申告書Bが2023年から統一様式となり、所得の種類にかかわらずこの様式を使用します。第一表には総所得金額や所得控除額を、第二表には所得の内訳や各種控除の明細を記入します。
●マイナンバーカードまたは通知カードのコピー
マイナンバーカードは、表面に顔写真と氏名・生年月日が、裏面にマイナンバーが記載された身分証明書です。一方、通知カードは顔写真がなく、マイナンバーと基本情報のみが記載された紙製のカードです。確定申告では、マイナンバーを確認できる書類として、いずれか一方が必要となります。
マイナンバーカードの場合は、表面と裏面の両方をコピーする必要があります。通知カードの場合は、記載内容が最新であることを確認の上、全面をコピーします。コピーは白黒でも問題ありませんが、文字や数字が明確に読み取れる必要があります。
●身分証明書(運転免許証など)のコピー
本人確認書類として認められるのは、以下の書類です。
・運転免許証
・パスポート
・在留カード
・住民基本台帳カード(写真付き)
・公的機関発行の顔写真付き身分証明書
身分証明書は有効期限内のものを使用し、顔写真と記載事項が明確に確認できるようにコピーします。運転免許証の場合、表面のみのコピーで構いません。なお、マイナンバーカードを提出する場合は、別途の身分証明書は不要です。
収入に関する書類
●源泉徴収票
源泉徴収票は毎年1月末までに勤務先から発行されます。この書類には年間の給与総額、所得税の源泉徴収額、社会保険料の控除額など、確定申告に必要な重要情報が記載されています。紛失した場合は、勤務先の給与担当部署に再発行を依頼できます。
源泉徴収票を受け取ったら、以下の項目を必ず確認します。支払金額の合計、源泉徴収税額、社会保険料等の控除額、扶養控除等の申告内容が実際の状況と一致しているかを確認します。特に年の途中で扶養家族や住所に変更があった場合は、その内容が反映されているか注意が必要です。
●収入の明細書または帳簿
副業の収入明細書には、取引の発生日、取引内容、収入金額を時系列で記録します。取引先の名称、支払方法、請求書番号なども併せて記録しておくと、後で確認が必要になった際に便利です。収支の区分を明確にするため、副業専用の口座を開設して管理することを推奨します。
経費に関する書類(必要経費を計上する場合)
副業の確定申告では、経費として計上する全ての支出について、適切な証明書類が必要です。これらの書類は税務調査の際の重要な証拠となるため、適切な保管と管理が求められます。
●領収書とレシート
支払いの証明には、取引内容、金額、日付、発行者が明記された領収書またはレシートが必要です。感熱紙のレシートは経年劣化で文字が消えることがあるため、コピーまたはスキャンデータとしても保存します。また、取引の内容が明確になるよう、必要に応じて補足メモを添付します。
●クレジットカードの明細書
クレジットカードで支払った経費は、カード会社の利用明細書に加えて、個々の取引の領収書も保管が必要です。事務用品購入や通信費支払いなど、定期的な支出については、契約書や利用明細も合わせて保管します。経費と私費の区別を明確にするため、副業専用のカードを作ることを推奨します。
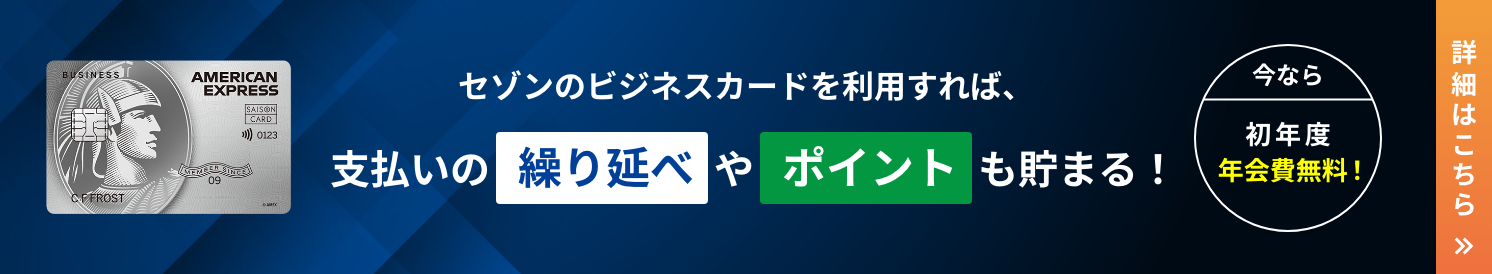

●交通費の記録
業務に関連する交通費は、移動の証明として以下の書類が必要です。これらの記録は、業務との関連性が明確に説明できるよう、訪問先や目的も併せて記録します。
・電車・バス:ICカードの利用履歴または切符の領収書
・タクシー:領収書(利用区間と目的を記録)
・自家用車:走行距離と燃料費の記録
控除に関する書類
確定申告で各種控除を受けるためには、適切な証明書類の提出が必要です。これらの書類は控除額の計算根拠となるため、確実に保管し、申告時に漏れなく提出することが重要です。
●生命保険料控除証明書
生命保険料控除を受けるには、保険会社から毎年10月から11月頃に送付される控除証明書が必要です。この証明書には、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の年間支払額が記載されています。複数の保険に加入している場合は、すべての証明書を保管します。紛失した場合は、各保険会社に再発行を依頼することができます。
●小規模企業共済の掛金証明書
小規模企業共済に加入している場合、中小企業基盤整備機構から送付される掛金証明書が必要です。この掛金は全額が所得控除の対象となり、確定申告時に大きな節税効果が期待できます。証明書は毎年10月頃に送付され、年間の掛金支払額が記載されています。
●医療費の領収書
医療費控除を申請する場合は、病院や薬局での支払いを証明する領収書が必要です。領収書には医療機関名、支払者名、支払日、支払金額が記載されている必要があります。また、2017年分の確定申告からは「医療費控除の明細書」の添付が必須となり、領収書の提出は不要となりましたが、領収書は5年間の保管が必要です。
●寄附金控除証明書
ふるさと納税や認定NPO法人への寄附を行った場合、寄附金控除を受けるには受領証明書が必要です。ふるさと納税の場合は、自治体から送付される寄附金受領証明書と、ワンストップ特例申請を行っていない証明書が必要です。寄附金控除証明書は原本の提出が求められるため、コピーを取って保管しておくことをお勧めします。
青色申告をする場合の追加書類
青色申告は、事業所得や不動産所得を正確に申告するための制度です。通常の確定申告書類に加えて、特定の財務書類の提出が必要となります。これらの書類は、事業の収支状況を詳細に示すものです。
●青色申告決算書
青色申告決算書は、1年間の事業活動の収支を明確に示す重要書類です。この決算書には以下の内容を記載します。
・収入金額や売上高の内訳
・仕入高と期末棚卸高
・経費の詳細な内訳
・専従者給与や青色申告特別控除額
クラウド会計ソフトを利用すると、日々の取引データから自動的に決算書を作成できるため、作業の効率化が図れます。特に、取引が多い事業者にとって、デジタル管理は大きな助けとなります。
●貸借対照表・損益計算書
青色申告特別控除の最大額65万円を受けるためには、複式簿記による記帳に基づいた貸借対照表と損益計算書の提出が必須です。これらの書類には以下の項目を正確に記載する必要があります。
・貸借対照表の主要項目
・事業用の現金預金残高
・固定資産の状況
・借入金や未払金の残高
・事業主貸や事業主借の金額
・損益計算書の主要項目
・売上高と売上原価
・販売費及び一般管理費
・営業外収益と営業外費用
・当期純利益または純損失
正確な財務書類を作成するためには、日々の取引を適切に記録することが不可欠です。取引発生時には、日付、取引内容、金額を明確に記録し、証憑書類との整合性を確認します。また、定期的な残高確認と帳簿の照合を行うことで、申告時の作業がスムーズになります。
副業特有の書類例
●インボイス登録番号の通知書
2023年10月から開始されたインボイス制度により、課税事業者となる場合は、インボイス登録番号の通知書が必要となります。年間の課税売上高が1,000万円を超える見込みがある場合は、課税事業者となる必要があり、税務署への登録申請が必須です。登録後発行される「適格請求書発行事業者登録通知書」は、確定申告時の添付書類として保管します。
●株式投資や仮想通貨の取引明細
投資活動による収入を副業として申告する場合、特有の書類が必要となります。
<株式投資の場合(証券会社から発行)>
● 年間取引報告書
● 特定口座年間取引報告書
● 配当金等の支払調書
● 譲渡損益に関する計算書
<仮想通貨取引の場合(取引所から入手できる書類)>
● 年間取引履歴
● 損益計算書
● 入出金履歴
● 各取引の約定明細
● 取引記録の管理
投資収入の申告では、取引の時系列での記録が重要です。売買のタイミング、取引価格、手数料などを正確に記録し、損益計算の根拠となる書類として保管します。特に仮想通貨取引では、複数の取引所を利用する場合、すべての取引所の記録を統合して管理する必要があります。
確定申告で活用できる節税制度と控除
小規模企業共済やiDeCoを活用した節税
小規模企業共済とiDeCoは、副業収入のある方が活用できる効果的な節税手段です。小規模企業共済は月額最大70,000円まで全額所得控除の対象となり、将来の生活保障にもなります。iDeCoは年間最大816,000円(自営業者の場合)まで所得控除が可能で、老後資金の形成と節税を同時に実現することができます。
所得控除(基礎控除、医療費控除など)の仕組みと種類
所得控除は、課税所得金額を計算する際に、収入から差し引く制度です。一方、税額控除は算出された税額から直接控除される仕組みです。例えば、所得が500万円で40万円の所得控除を受けた場合、課税所得は460万円となります。
主な所得控除の種類と内容を以下で紹介します。
①基礎控除
所得金額2,500万円以下の場合、一律48万円が控除されます。所得金額が2,400万円を超えると控除額が段階的に減少し、2,500万円を超えると控除を受けることができません。
②医療費控除
計算式:(支払医療費 - 保険金等で補填される金額)- 10万円
通院費、入院費、薬代に加え、通院のための交通費も対象となります。生計を一緒にする家族の医療費も合算することができます。
③社会保険料控除
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など、支払った社会保険料の全額が控除対象となります。給与から天引きされる場合は年末調整で自動的に控除され、個人で支払う場合は確定申告で申請します。
④生命保険料控除
控除可能な金額を以下で紹介します。新契約(2012年1月以降)と旧契約では控除限度額が異なります。
生命保険料:最大40万円
介護医療保険料:最大40万円
個人年金保険料:最大40万円
●⑤配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者の年間所得が48万円以下の場合、配偶者控除(最大38万円)を受けられます。配偶者の所得が48万円超133万円以下の場合は、配偶者特別控除の対象となります。ただし、納税者本人の所得制限があり、所得が1,000万円を超えると控除額が段階的に減少します。
副業の確定申告の申請方法
①確定申告申請書の作成
確定申告書の作成には複数の方法があり、自身の状況に合わせて選択できます。
・国税庁の確定申告書作成コーナー
国税庁のウェブサイトで提供される無料のオンラインサービスです。画面の案内に従って入力するだけで、必要な書類を作成できます。スマートフォンにも対応しており、マイナンバーカードがあればe-Taxでの提出まで完結できます。
・確定申告会場での相談
税務署に設置される確定申告会場では、税理士や職員による個別相談を受けながら申告書を作成できます。ただし、2月から3月は混雑するため、事前予約が推奨されます。初めて確定申告を行う方や、複雑な申告内容がある方に適しています。
・クラウドサービス・ソフトウェア
民間企業が提供する確定申告支援サービスでは、より使いやすいインターフェースと、年間を通じた収支管理機能が利用できます。特に、青色申告を行う場合や、複数の収入源がある場合に便利です。
・手書きでの作成
従来の方法として、用紙に直接記入する方法もあります。税務署で用紙を入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードして使用します。
②確定申告書の提出
確定申告書の提出方法を以下で紹介します。
・e-Taxによる電子申告
最も推奨される提出方法です。24時間いつでも提出可能で、添付書類の提出省略が可能、還付金の受け取りが早いなどのメリットがあります。
・郵送による提出
確定申告書と必要書類を封筒に入れて税務署に郵送します。控えが必要な場合は、返信用封筒を同封します。配達記録や簡易書留の利用で、確実な提出が可能です。
・税務署への持参
直接税務署の窓口に提出する方法です。書類の不備がある場合はその場で指摘を受けられますが、確定申告期間中は窓口が混雑します。また、新型コロナウイルス感染症対策として、できるだけ非対面での提出が推奨されています。
副業の強い味方!「セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®️・カード」
副業を認められている会社に勤めている方で、これから副業を始めようというときは、経費の支払いや納税用にビジネスカードを1枚作っておくと便利です。セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®️・カードなら、経費の支払いや所得税の納税でポイントを貯められるだけでなく、ビジネスに役立つ優待もたくさん受けられます。
さらに法人口座を引き落とし口座に設定できるため、プライベート利用とビジネス経費処理のための面倒な仕分けも必要ありません。このビジネスカードは経費管理と業務の効率化に最適な1枚で、副業にとっての強い味方です。現在初年度年会費無料キャンペーンも実施しています。