デジタルトランスフォーメーション(DX)とは?IT化やデジタル化との違いと成功事例4選
本記事では、改めてデジタルトランスフォーメーションが何を意味し、世の中や私たちの暮らしがどのように変貌を遂げていくのかについて考察します。そして、変化をけん引している代表的な企業をピックアップしてご紹介します。
デジタルトランスフォーメーションは単なるIT化やデジタル化ではない
デジタルトランスフォーメーション(DX)はスウェーデンのエリック・ストルターマン教授が最初に唱え始めた言葉だと言われています。「目覚ましい進歩を遂げているIT(Information Technology)が人々の生活をあらゆる面でより豊かに変化させること」だと彼は定義しています。もっと簡潔に言い切ってしまえば、「デジタルによる世の中の変革」です。
振り返れば、インターネットが普及し始めた90年代の末期に「IT革命」という表現がやたらと用いられました。確かにインターネットの普及前と普及後では世の中が激変し、見違えるほど便利になっていることからデジタルトランスフォーメーションに該当するでしょう。
ただ、現在取り沙汰されているデジタルトランスフォーメーションとは、これから先のことを指しています。ちなみに、デジタルトランスフォーメーションの略称が「DX」であるのは、英語におけるtransの略記がXとなるからです。
デジタイゼーション、デジタライゼーションとの違いとは?

世間では「デジタルトランスフォーメーション=デジタル化」と捉えられることが多いですが、それは大きな誤解です。また、同じくデジタル化と訳されるデジタイゼーション(Digitization)とデジタライゼーション(Dizitalization)についても、それぞれの真意は異なっています。この章ではそれぞれの違いについて解説します。
アナログからデジタルへ移行する「デジタイゼーション」
デジタイゼーションとは、アナログからデジタルへの移行を図るフェーズを意味しています。典型的な例が手書きからテキストデータへの転換です。デジタル技術を用いて業務の効率化や合理化を図ることがその目的です。
デジタル化による新たな価値や利益の創出を示す「デジタライゼーション」
デジタライゼーションはさまざまなプロセスがデジタル化されたことが新たな価値や利益を創出することを示しています。つまり、デジタル化によって新たなビジネスが生まれることこそ、デジタライゼーションなのです。
たとえば通信技術の発達でわざわざCDを購入せずともインターネット上で容易に音楽をダウンロードできる環境が整ったことで人々の音楽に関する購買行動がCDの購入からネット上でのダウンロードへとシフトしました。
さらに、特定の音源をダウンロードするのではなく、定額料金で聴きたい放題というストリーミング(サブスクリプション制)のサービスが誕生し、急速に支持を集めるようになっています。これらはデジタル化が進み、新たな価値や利益を生み出すデジタライゼーションの典型的な例です。
他の分野でも、カーシェアのように「モノを所有する」ということが過去の常識となれば、人々の暮らしは劇的に変わります。言い換えれば、様々な分野で発生したデジタライゼーションがデジタルトランスフォーメーションをもたらすということです。
その観点から整理すると、本当の意味ではデジタルトランスフォーメーションの推進をけん引できる企業はかなり絞られてくることになるでしょう。冒頭でも触れたように、多くの企業が重要施策と位置づけているものの、その実態はデジタイゼーションにすぎないケースが散見されるからです。
着実にデジタライゼーションをもたらし、その新たなビジネスが世の中に広く受け入れられ、人々の暮らしぶりにも大きな影響を及ぼし始めることこそ、真のデジタルトランスフォーメーションを推進する企業と言えるでしょう。
社会を変革したデジタルトランスフォーメーションのビジネス事例
この章ではデジタルトランスフォーメーションによって社会を変革したビジネス事例を4つ紹介します。
事例1:新たな配車サービスを生み出した「Uber」
世界におけるDX推進企業の筆頭としては、やはり誰もがGAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)を挙げることでしょう。ですが、米国では他にも世の中の常識を塗り替える企業が多数登場しています。
その一例がウーバー・テクノロジーズ(Uber Technologies)です。日本では法律に抵触するため、基幹事業であるライドシェアを展開できず、コロナ禍でニーズが急拡大しているUber eatsのほうにスポットが当たりがちです。
しかしながら、ウーバーが創出した配車サービスのプラットフォームは世の中を大きく変えました。移動したい人と空き時間で収入を得たいドライバーをマッチングさせることで、今までタクシーが配車されていなかったエリアまでカバーできるようになっています。
しかも、クレジットカード決済でドライバーとは金銭のやりとりを直接行わないため、法外な料金を請求されるようなタクシーにありがちなトラブルも回避されます。
事例2:中国EC市場最大手の「アリババ」
「IT革命」の時代と呼ばれた1999年に創業し、中国のEC市場で最大手となっているアリババグループ(阿里巴巴集団)も、DXの旗手と言える存在です。
現在、同グループは中国において下記のようなさまざまな事業を展開しています。
・B to Bのeコマース「アリババドットコム」
・B to Cのeコマースサイト「T mall(天猫)」
・越境eコマースサイト「T mall Global(天猫国際)」
・C to Cのeコマースサイト「タオバオマーケットプレイス」
・決済サービス「アリペイ」
・クラウドサービス「アリババクラウドコンピューティング」
最近、アリババグループの取り組みで特に話題に上っているのは、新業態のスーパーマーケット「盒馬鮮生(フーマー)」です。オンライン(eコマース)とオフラインの店舗を組み合わせたユニークなビジネスは、ひときわ異彩を放っています。
陳列されている商品にはQRコードが付いており、来店客は生産地やアレルギー情報などの詳細を確認できる一方、管理する側も割引などの価格変更を遠隔操作できます。日本の小売業も導入しているように、無人レジの設置や購買履歴に基づいた在庫管理は当然のこととなっています。
さらに「盒馬鮮生」は海鮮コーナーに活魚が泳ぐ生け簀を設置し、その中から購入したものを選べるようなエンターテインメント性も演出しています。
なお、アリババグループは2014年に「すべてのデータを業務化する」との理念に基づいて、デジタルミドルオフィスプラットフォーム(数字中台)という体制を確立させています。デジタルミドルオフィスプラットフォームとは、フロントオフィスとバックオフィスの中間に位置するものです。
フロントオフィスを縮小してミドルオフィスに大きな役割を持たせることで、ビジネスを取り巻く環境の変化に迅速に応えられる管理構造を構築したのです。これはデジタライゼーションの一環であり、こうした体制固めがDXをもたらしていくことになります。
事例3:スマホで誰でも物を売れるようにした「メルカリ」
日本においても、これまでの世の中の常識を塗り替えた企業が登場しています。多くの人々がもはや当たり前のように利用しているフリーマーケットアプリのメルカリです。同社の登場以前は、個人間(C to C)の取引で用いられていたのは主にオークション方式でした。
日本国内でオークション方式はあまり馴染み深い存在ではなく、ヤフオクなどのサービス利用者の拡大にも限界があったと言えます。ですが、メルカリはスマートフォン上のアプリで誰もが容易に出品・購入が可能となるプラットフォームを構築し、一気に個人間取引のマーケットを拡大させました。
現金同等物や高値転売目的の出品など、いくつかの問題が生じたことは確かですが、匿名での出品・配送・購入が可能な仕組みを作り出し、気軽に参加できる環境を整えた功績は大きいでしょう。
そして、メルペイという決済サービスも導入し、メルカリ内はもちろん、他業界のリアルな店舗でも利用できる利便性を提供しています。
事例4:オンライン×デリバリーを進める「マクドナルド」(US)
最後に取り上げるのは、ファストフード界の巨人、マクドナルドです。一見、ファストフードとDXにはあまり関連性が見られないように思えるかもしれません。
ですが、米国のマクドナルドは2017年にVelocity Growth Planという計画を発表し、6つをテーマに掲げてDXを推進することを表明しています。
下記が6つのテーマに掲げられた内容です。
・Retain(既存顧客の保持)
・Regain(失った顧客の再獲得)
・Convert(顧客のリピート顧客化)
・Digital(顧客体験のデジタル化)
・Delivery(マクドナルドでの体験をより多くの顧客に)
・Experience of the Future in the U.S. (テクノロジーの力で未来の体験を顧客に)
実は世界がコロナ禍に見舞われる数年前から、マクドナルドはオンラインでのオーダーと自前のデリバリーというサービス構築に動いていました。それは日本マクドナルドも同様です。
コロナ禍で他のファストフードがUber eatsに依存しながらデリバリーの需要に応えているのに対し、日本マクドナルドは自前の配送網を有しており、より多くの利益を確保できています。DX推進に6つのテーマを挙げているように、それはデリバリーだけに限った話ではありません。
密かにマクドナルド(米国)は、巨費を投じてAIのスタートアップを傘下に収めています。そして天候や時間帯、顧客の嗜好などに基づいてAIが個別最適化したメニューを提供するというシステムを米国や豪州のドライブスルー店舗に導入しているのです。
これらの店舗で実績が蓄積されてデータ分析が進んでいけば、個別最適化の精度はどんどん高まっていきます。それが進めば、顧客は自分で具体的にオーダーしなくても、オートマチックに求めているメニューが提供されることになります。
あらゆる業界がデジタルトランスフォーメーションに取り組んでいる
ウーバーやアリババグループのようなテック企業はもちろん、マクドナルドのような飲食業までデジタルトランスフォーメーションに深く関わっていることは意外だったかもしれません。世界中で同じ品質の同じメニューを味わえる体制を築いたという点で、過去にマクドナルドは世の中を大きく変えたと言えます。
ただし、それはテクノロジーよりもマネジメントの賜物でした。先述したVelocity Growth Planが推進されていけば、次はマクドナルドがデジタライゼーションによってファストフードのサービスを大きく変え、DXを実現させていくかもしれません。
このように、あらゆる業界においてデジタルトランスフォーメーションへの取り組みが進められています。

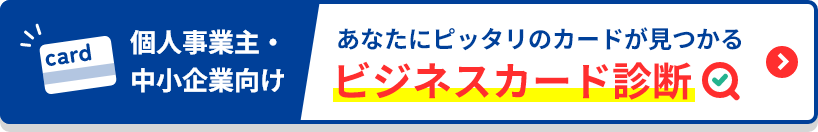
dx.png)
dx.png)

